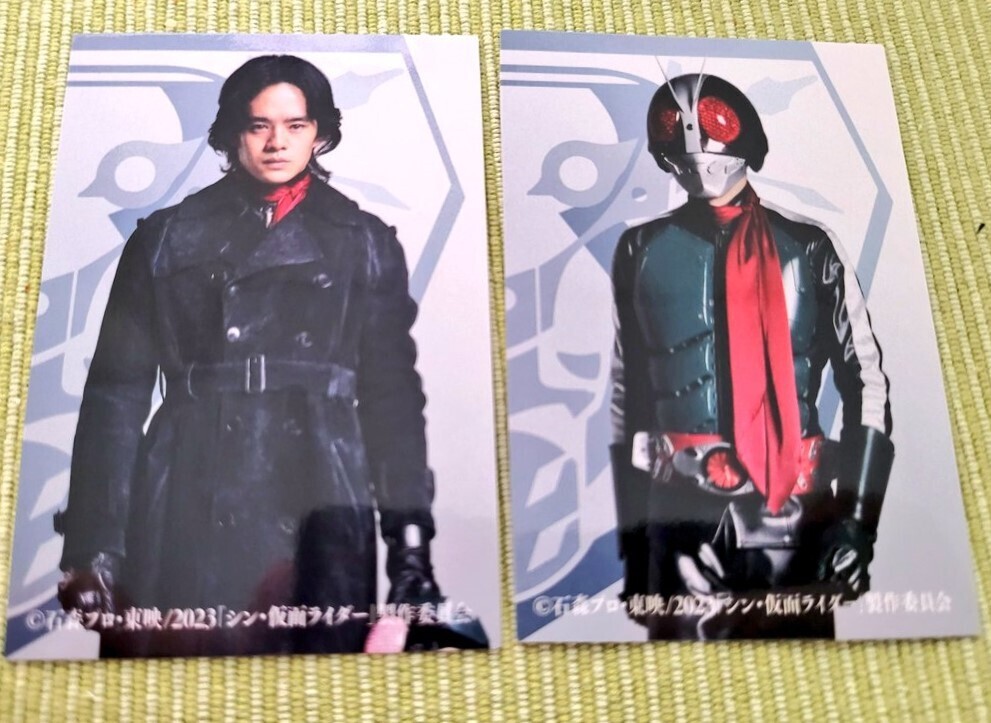Steam 版 FINAL FANTASY VII REMAKE のハードまでクリアしたので感想を。インターグレードは未プレイです。
良いリメイクだと思うが・・・・・・
オリジナルの FF7 はミッドガルが一番好きで、街中をもっと歩き回りたいと思っていました。REMAKE ではその夢が適い満足です。次は、VR かな。
ただ、クリア直後の感想としては、端的に冗長。エアリス救出後の神羅ビル脱出が無駄に長い。連戦に次ぐ連戦でセーブをする間も息をつく暇もない。ラストはイベント戦闘のため長い演出をカットすることすらできない。そして、CRISIS CORE FinalFantasy7 REUNION に続くことが分かっているので全然スッキリしない。
戦闘はアクション風で爽快感がある。演出もスピード感があり豪華。しかしながら、避けられそうで避けられない攻撃などがあって理不尽に感じる。また、混戦になると敵の前動作が見えないし、攻撃が飛んでくる方向も分からない。ハードだとザコ敵が多いだけで、分けの分からんピタゴラスイッチで死ぬことがある。
コマンドバトルなら敵の攻撃を避けられないのはお約束ですが、アクション風の戦闘のため避けられなさに理不尽さが増しているのでしょう。
FF のファンでしたが、もういいかなぁという気にさせられます。
ミッドガルの再現度がすごい
再現度ってなんだ。
オープニングのエアリスから引いていきミッドガルの全景が映し出させるムービーを見られただけで満足です。その後のクラウドが壱番魔晄炉を見上げるシーンも素晴らしい。
CG 技術の向上によるミッドガルの作り込みは、実在するかのような「再現度」を感じました。裕福で整然とした上層だけでなくごちゃそちゃとしたスラムや、上層とスラムをつなぐ中間層を歩くことで、ミッドガルを実感できます。テロによる被害もよりクッキリとなっており、それがティファやジェシーの心の内をよりクリアにしてもいます。
マップの構成は、FF10 や FF13 のような一本道ではありますが、クエストを適度にまぶし夜と昼とで別の顔を見せるなどの工夫もあり、歩き回るのが楽しい。
神羅ビルの大きさは更に際立ち、お金がかかっている感が半端ない。階段を実際に59階も昇らせるとは思わなかったけども。そして、トレイのあるゲームはやはりよいゲームだ。
補完されたストーリー
ストーリーはオリジナル版を補完しつつ、オリジナル版の結末をヴィジョンとして見せる演出になっている。
本筋はより濃厚になりつつ、枝葉も抑えている。ビックス、ウェッジにジェシーなどオリジナル版にも存在したキャラクターに深みが増している。ジェシーはよりかわいさと強さが増しましたね。生きているといいなぁ。
コルネオ関係ではキャラクターが増えており、コルネオの館へ女装して潜入するイベントも盛りだくさんとなっている。
ただ、アニヤンとのダンスはもっと他に方法がなかったのか。音ゲーになっているが、音ゲーに集中するとダンスが見えないし、ボタンを押すタイミングも分かりづいため、あまり褒められたミニゲームではない。
全体定期にミニゲームの作り込みはイマイチで、バイクイベントも不自由さが目立ち爽快感がない。スノーボードが心配だ。
しかし冗長
バイクイベントに限らず、補完が過ぎて冗長なシーンが多々ある。
チャプター15「落日の街」は落下した七番街を目に焼き付ける重要なシーンではあるのだが、一つのチャプターとする必然性がないように思う。
個人的に冗長すぎると感じるのは、冒頭でも述べたとおりエアリス救出後の神羅ビル脱出イベント。連戦に次ぐ連戦で休む暇がない。ルーファス戦後のエアリスとバレットとでハンドレッドガンナーと戦う前に、X 長押し*1によるメニュー開閉ではなく、確実にメニューを開かせるタイミングを作って欲しかった。
その後は、長いバイクイベント。流石に、制作陣も冗長と判断したのか周回時にはスキップできるようになっている。
最終章はほぼイベント戦で、そのためにムービーシーンをスキップできない。ただただ、操作できない時間が流れてつまらない。
オリジナル版とは異なる展開を匂わせる点で必要なイベント戦闘ではあるが、脱出して終わりと思っていたのもあり、ダラダラと続くなぁという印象しかなかった。これはハードで周回しても感想は変わらず。根本的に冗長なのどだと考えられる。
FF16 もこのバトル形式なら嫌だぜ?
全体的にボス戦はイベントバトルっぽくて自由度が低い。形態変化を必ず経由する必要があるため、HP を一気に削ることはできない。バーストを狙っていくのが基本戦術だけども、形態変化するとバーストがリセットされるため理不尽さがすごい。
理不尽さで言えば、避けられそうで避けられない攻撃が多いこと。一方で、魔法が避けられるのはどうかと思う。サンダーはほぼ必中のようだが。
また、カメラアングルも理不尽さを際立たせる。自由には動かせないし、混戦ともなると敵の攻撃がどこから飛んでくるのか全然分からない。
敵が多いとターゲットを固定化するのもままならない。神羅ビル脱出時に出現するハンドレッドガンナーは弱点を晒すが、ターゲットが多く操作性も悪いため、弱点に狙いを付けるのも難しい。
インターグレードをクリアすると挑める裏ボスは攻略方法を見る限り、ELDEN RING のマレニアっぽいのだが、このバトルシステムでマレニアと戦うのは理不尽さが半端なさそう。
後味が悪い
ムービーシーンの多いゲームは、もう自分向きではないのだろう。以前ならムービーのすごさに引きつけられていたが、CG のすごさだけでは自分の心は動かないし。むしろ、その中を自由に歩かせろと。
小島秀夫作品もムービーシーンが多く、さっさとキャラクターを操作させろ!と感じるのですが、それを超える自由度がワクワクさせられるからこそプレイしている。
FINAL FANTASY VII REMAKE はミッドガルを探索する楽しさはあったし、ストーリーも原作から補完されていてワクワクするけれども、最後の最後で冗長さが気になってしまった。最後の最後で冗長だし、本作で完結するわけでもないため後味が悪いので当然だろうが。